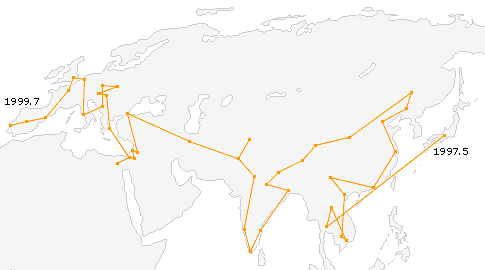翌朝、私はこの日も一番後に宿を出た。
レイケたちに追いつき追いこす。
後ろからレイケが何か叫んでいる。
振り向くと、レイケが違う道を指さしている。
どうやら道を間違えたようだ。
いま来た道をもどってゆく。
方向音痴な私は、よく道に迷う。
一度などは、目的地まで半日で行けるところを道に迷い、到着したのが翌日の昼だったこともあった。
「ありがとう」
私はレイケに感謝した。
カリコーラに先についた私は、適当な食堂に入り、簡単に食事をした。
ホットレモンも飲みおえ、そろそろ行こうかと思ったとき、レイケたちがやってきた。
すれ違いに出てゆくのは失礼だろうと思い、私は彼女らとおしゃべりをした。
その中で私は、「結婚についてどう思う」
と彼女らに聞いてみた。
このときレイケは私と同じ27歳、眼鏡の彼女は28歳だった。
彼女らは、私が、私と結婚しないかと聞いたかと思い、「私たちはクリスチャンとしか結婚はしない」
と婉曲に私を断ろうとした。
「違う、違う」
と私は言い、私は欧米人女性の結婚観を聞きたいのだ、と言った。
これがまずかった。
彼女らの感情に火をつけてしまった。
「多くの人たちが20歳くらいで安易に結婚してしまうけど、彼らの離婚率が高いのは事実だわ。それはもちろん幸せに結婚生活をおくっているカップルもいて、私も彼らみたいになりたいとは思うけど。結婚してすぐ離婚してしまうなんて、ナンセンスだわ。それだったら私は、良い人をじっくり探して幸せになれる結婚をしたい」
それを正論だと思った私は、彼女らにそれを話したが、彼女らの感情の高ぶりはそれぐらいでは収まらず、彼女らの感情が落ちつくまで、彼女らの言い分を聞くはめになった。
彼女らが、自分の言っていることが正論だと信じながらも、それを気にしているところもあるからなのだろう。
それに、レイケは感情が高ぶりやすい女性だということを忘れていた。昨晩も一昨日の夜もそうだったが、夕食時に自然と始まる旅の話のときはよく感情的になって話していた。
――つまらない質問など、するものじゃないな。
私は反省した。
途中、山道の疲れが残っているのか、眼鏡の彼女は休憩すると言った。
レイケと私も休憩しようとするが、「追いつくから先へ行っていて」と言われ、先に進むことにした。
「ハローペン、ハローペン」
これはトレッキング中、地元の子どもからよく受けるあいさつである。
その意味を日本語に直すと、「こんにちは、ペンをください」となる。
私はそう言われる度に、「俺はペンじゃない。某だ」
と答えていた。
このときもそう言った。
レイケもそれにつづく。
「私はペンじゃない。レイケよ」
笑われるかもしれないが、私はこのときレイケに相棒、同士のようなものを感じた。
レイケに子どもが何かを言い返した。
放っておけばよいのだが、レイケは彼らに何か言い返す。
その途端、子どもたちとレイケは、手や持っていた杖を銃に見立て、銃撃戦をはじめた。
手でピストルを作りバン、バンという子どもたちに対して、レイケの杖はマシンガンだ。
「ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ」
勝負はあっけなくついた。
気の利いた子どもたちがやられたふりをすると、レイケは銃口の煙に、ふうと息をかけ、「さあ、行きましょう」
と言った。
きついのぼり坂をのぼり、ブプサの村についた私は、茶店でララヌードルスープを頼んだ。
ララヌードルスープはネパールの定番インスタントラーメンである。
私がそれを食べおわるころ、レイケが坂をのぼってきた。
屋外のテーブルについていた私は、レイケに声をかけた。
彼女は、「ああ疲れた」と言いながら私の隣に座った。
「あなたがここに着いてから、私がここに来るまで何分経った?」
時計を見ていなかった私は、どれくらいだったかなと思いだそうとした。
「二十分くらい?」
「十五分くらいかな」
そう答えると、彼女は喜んで、何にしようかなとメニューを見はじめた。
「この店はコーヒーが安い」
どうやら他の店より安いらしい、「今日はついている」と言って彼女は無邪気に喜び、コーヒーを注文しにいった。
戻ってきた彼女は私の向かいに座り、バックパックからスニッカーズを取り出すと、「最後の一本だけど食べちゃおう」
と言って、おいしそうに食べはじめた。
スニッカーズ、ピーナッツをチョコレートで包んだもので、私は日本にいるときはTVのCMを見ても、それを食べたいなどと一度も思ったことがなかった。
が、トレッキングをはじめて十日目のいま、嗜好品に飢えていた私は、彼女がそれを食べているのを見て、「買ってくる」
と店に入った。
店の奥さんにスニッカーズの値段を聞くと、90ルピー(約180円)と言う。
ここは山奥だから仕方がないが、この値段はカトマンズで同じものの倍の値段で、ここではダルバートよりも高い。
貧乏旅行者である私は迷いに迷ったが、スニッカーズはあきらめ、15ルピー(約30円)ほどのビスケットを二つ買った。
テーブルに戻った私は、レイケに、「高かったから買わなかったよ」と言った。
「半分食べる?」
彼女は私に食べかけのスニッカーズを勧めてくれた。
「ありがとう、でもやめとくよ」
私はその理由を、「ナムチェのバザールへ行けばカトマンズと同じ値段で買えるから」と話した。
スニッカーズを勧めてくれたお礼にと、私はビスケットの袋をやぶいて彼女にそれを勧めた。
袋をやぶいたときに、テーブルの上に散らばってしまったビスケットをあつめていると、その手の中に半分に折られたスニッカーズが飛びこんできた。
私は咄嗟にレイケを見た。
「あなたのものよ」
彼女はそう言って、微笑んだ。
その瞬間、私は彼女をたまらなくかわいらしく感じ、そして、彼女に恋をした。
私はお礼を言った。
そして、ナムチェのバザールでスニッカーズを二本手に入れて、レイケにプレゼントすると約束した。
「絶対よ。約束だからね」
私は充分に休憩したのと、レイケに対して学生のころのような恋心を抱いたことが、なにやら気恥ずかしいのとで、先に進むことにした。
「僕は今日、チュトックまで行くよ」
と言うと、レイケは、「友達はここまで来るのが精一杯だろうから、たぶん今日はここに泊まるわ」と言った。
私たちは、「サヨナラ」を言って別れた。
道中、私はレイケのことばかりを考え、レイケに対する自分の気持ちに自問自答を繰り返した。
――おまえはスニッカーズをもらったから好きになったのだ。
――違う。ここ数日、毎日彼女とふれあって、徐々にそう思っていたのだ。スニッカーズは好きになる最後のきっかけに過ぎない。
――だったらなぜ、彼女から離れようとする。
――今日の目的地がチュトックだからだ。
25歳までの人生を女性に振り回されて過ごしてきた私は、女性のために自分の予定を変更することを嫌っていた。
チュトックに着き、宿を決め、夕食を済ますと、私はドミトリーのベッドに寝転がった。
宿の天井を眺めながら、私は、ここ数日、毎日レイケといっしょだったことを思い出し、なぜ今日はいっしょではないのかと思い、そのことにさみしさを感じた。
「また、彼女に会えるだろうか」
私はひとり、つぶやいてみた。
いとう某 22歳のとき初めて行った海外旅行で日本とは違う世界に衝撃を受ける。まだ見ぬ世界、自己の成長と可能性を求めて旅した国は、5年間で35ヶ国。思い出に残る旅はエヴェレストを見たヒマラヤトレッキング。